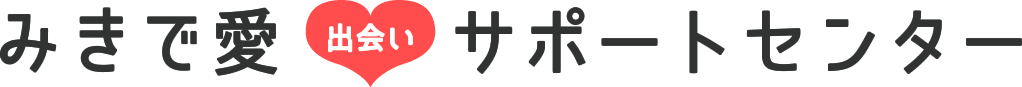〜「赤い糸プロジェクト」のお知らせ〜
担当者不在で対応できないケースもございますので、必ず事前にご予約ください。
平日(月曜日~金曜日)※祝日除く
9:00~16:00
※お昼休み(12:00~13:00)・年末年始を除く
三木市役所 縁結び課 4F
みきで愛(出会い)サポートセンター
〒673−0492 三木市上の丸町10番30号
TEL 0794−82−8833(平日8:30〜17:00)
E-mail mikideai@city.miki.lg.jp
〒673−0492 三木市上の丸町10番30号
TEL 0794−82−8833(平日8:30〜17:00)
E-mail mikideai@city.miki.lg.jp